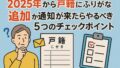引越しが決まると、荷造りやライフラインの手配など、準備に追われてしまいます。しかし、新しい生活を問題なく始めるためには「役所での手続き」が欠かせません。住所が変わることで、住民票・健康保険・年金・印鑑登録など、自治体に届け出なければならない手続きがいくつもあります。
特に初めて引越しをされる方は、「どこで何をすればいいの?」「期限は決まっているの?」と不安になるのではないでしょうか。
本記事では、
✅何から手続きすれば良いか
✅必要な書類は何か
✅期限はいつまでか
✅混雑を避けるコツ
を わかりやすく、順番に解説 しています。
初めての引越しでも迷わず進められる「保存版ガイド」です。
スムーズな新生活スタートのために、ぜひチェックしてください。
1. 引越しに伴う「役所手続き」の基本

引越しをすると、新しい住所で暮らしを始めるために、住所変更や各種行政サービスの受給先の変更が必要になります。
住民票や印鑑登録、保険・年金など、手続きをしないままだと「証明書が取れない」「保険が使えない」「行政サービス対象外」といった事態になる可能性があります。
また、引越し後14日以内に手続きを行うことが法律で定められています。
この章では、なぜ「役所手続き」が必要なのか、いつまでに何をする必要があるのか、まずは基本を押さえておきましょう。
2. ステップ1:転出届の提出(旧住所)

■ 転出届とは?
別の市区町村へ引越す際に、旧住所地の自治体へ提出する届け出です。
手続きをすると「転出証明書」が発行されます。
新住所での手続きに必要となるため、失くさないように保管しましょう。
■ 提出時期と場所
- 引越し予定日の14日前から提出可能(自治体によっては約1か月前から可の場合もあります)
- 旧住所地の市役所・区役所・町村役場で手続き
- 郵送・オンライン対応の自治体もあり
■ 必要書類
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 印鑑(原則不要)
■ 手続きできる人(転出届)
転出届は、 基本的には本人 が届け出を行います。
ただし、次の方も手続き可能です。
- 本人
- 同一世帯の家族(配偶者・親・子など)
- 代理人(委任状が必要)
※委任状を使用する場合は、本人が署名した委任状と、代理人の本人確認書類が必要です。
※別世帯の親族や知人の場合も、委任状があれば手続きできます。
■ よくある注意点
- 同一市区町村内は「転居届」でOK(転出届は不要)
- 転出証明書の紛失に注意
3. ステップ2:転入届・転居届の提出(新住所)

■ 転入届と転居届の違い
- 転入届:他の市区町村から移ってきた場合
- 転居届:同一市区町村内の引越しの場合
■ 提出期限
- 新住所に住み始めてから 14日以内
遅れた場合も受理されることが多いですが、理由を求められるケースがあります。
また14日を過ぎると、マイナンバーカードが失効してしまう可能性があるので注意が必要です。
■ 持ち物
- 転出証明書(転入届の場合)
- 本人確認書類
- 印鑑は原則不要(印鑑登録をする場合は、登録する印鑑が必要)
- マイナンバーカード(持っている場合)
■ 手続きできる人(転入届・転居届)
転入届も、 原則として本人 が手続きを行います。
ただし、以下の方も届け出ができます。
- 本人
- 同一世帯の家族(転入・転居後に同一世帯の人)
※転入・転居前に同一世帯でも、転入・転居後に別世帯になると原則委任状が必要です。 - 代理人(委任状が必要)
代理人が手続きする場合は、
- 本人が記載した委任状
- 代理人の本人確認書類
の持参が必要です。
4. ステップ3:印鑑登録・住民票・マイナンバーカード

■ 印鑑登録
県外や市外など、違う自治体へ引越しする場合は、転出と同時に印鑑登録も廃止されます。
印鑑証明を利用する予定がある場合は、新住所(新住所の自治体)での登録が必要です。
市内転居など、同じ自治体内での引越しは、転居届だけで大丈夫です。
■ 住民票の変更
転入届の提出を終えると、新住所で住民票が取得できるようになります。
■ マイナンバーカードの住所変更
表面に新住所が記載されます。
オンライン手続きや本人確認がスムーズになります。
5. ステップ4:国民健康保険・年金などの生活関連手続き

■ 国民健康保険
・加入者は住所変更が必要
・遅れると保険証が使えない場合あり
■ 年金・児童手当・介護保険
・住所変更により、担当窓口や受給に影響が出ることも
・子どものいる家庭は、学校・保育園の手続きも早めに
6. 地域差に注意!市区町村や県またぎの手続き

■ 市区町村によって異なるポイント
- 持ち物
- 窓口の受付時間
- オンライン申請の有無 など
事前に自治体サイトをチェックしておくと安心です。
■ 県をまたぐ引越し
「転出届 → 転入届」 の順番を必ず実施
転出証明書の扱いが異なるポータルもあるため注意
7. よくあるトラブル&スムーズに進めるコツ
■ よくあるトラブル例
- 旧住所地で転出の届をしていない。
- 転出証明書を忘れたなど、必要書類不足で再訪問
- 14日以内の届け出を忘れた
- 窓口の混雑で長時間待ち
- 手続きをする資格がない(委任状が必要となる場合など)
■ 対策
- 必要書類チェックリストを作成
- 平日午前中や予約制度の活用
- オンライン手続きできるか確認
✅役所手続きチェックリスト(コピー用)
- 転出届(旧住所)
- 転入/転居届(新住所)
- 住民票の移動確認
- 印鑑登録の変更
- マイナンバーカード住所変更
- 国民健康保険手続き
- 年金・児童手当など各種変更
- 子ども関連の手続き(学校・保育)
- 期限(14日以内)厳守
まとめ:手続きは早めに動いて、新生活を安心スタート!
引越しに伴う役所手続きは、
①転出届 → ②転入(または転居)届 → ③印鑑登録や保険などの付帯手続き
という順番で行うことでスムーズに進められます。
特に次のポイントを押さえておきましょう👇
- 14日以内の届け出を守る
- 必要書類を事前にまとめておく
- 平日午前中や予約制度を活用して混雑回避
- マイナンバーカードやオンライン申請をうまく活用
「あとでやればいいか」と後回しにすると、
保険証が使えない・証明書が取れないなど生活に支障が出ることもあります。
引越し準備の段階からスケジュールを立て、漏れなく進めることで、
新生活を安心してスタートできます。
📌 あわせて読みたい