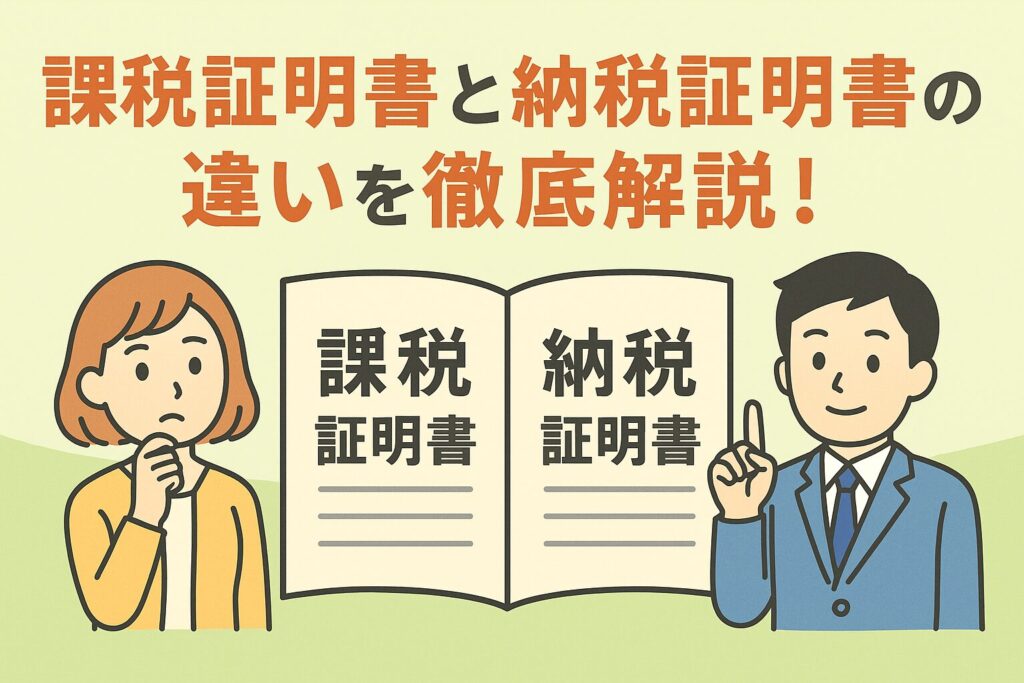税金に関する手続きで「課税証明書」や「納税証明書」を提出してください――。
そんな案内を受けたことはありませんか?
どちらも“税金”に関する書類ですが、証明している内容と発行する場所がまったく異なります。
この記事では、両者の違い・使い分け・発行方法を、初心者にも分かりやすく丁寧に解説します。
🔰まずは基本理解:課税証明書と納税証明書の違い
| 証明書名 | 発行機関 | 証明内容 | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| 課税(所得)証明書 | 市区町村役場 | 前年の所得金額・住民税の課税額 | 住宅ローン、保育園申請、奨学金、各種手続き |
| 納税証明書 | 税務署または自治体 | 実際に納めた税金の金額・納税済みの事実 | 税務調査、入札、ローン、補助金手続き |
👉 発行元が違うのが最大のポイントです。
- 課税証明書:市区町村(住民税関連)
- 納税証明書:税務署(所得税・法人税など国税)または自治体(住民税など地方税)
🧾課税証明書とは?

課税証明書は、「その人の所得と課税状況」を証明する書類です。
正式名称は「課税(所得)証明書」で、市区町村が発行します。
内容
- 前年の所得額
- 所得控除の内容
- 住民税額
- 扶養の有無
- 所得区分(給与所得・年金所得など)
こんなときに必要
- 住宅ローンや賃貸契約の審査
- 保育園・幼稚園の入園手続き
- 奨学金や各種補助金申請
- 高校・大学の授業料免除手続き
- 所得証明を求められたとき(例:婚姻届提出時など)
注意点
- 前年1月〜12月の所得に基づいて、翌年6月から発行されます。
例)令和7年度分 → 令和6年中の所得を記載 - 非課税の人でも「非課税証明書」として発行されます。
- マイナンバーカードがあれば、コンビニでも取得可能(全国の多くの自治体で対応)。
💴納税証明書とは?

納税証明書は、「実際に税金を納めたこと」を証明する書類です。
国税(所得税・法人税など)は税務署、地方税(住民税・固定資産税など)は自治体で発行されます。
税務署で発行される納税証明書(国税)
国税庁が発行する納税証明書にはいくつかの種類があります。
| 種類 | 内容 | 主な用途 |
|---|---|---|
| その1(納税額証明) | 所得税などの納付済み金額 | 融資・入札・補助金申請 |
| その2(未納のない証明) | 未納税額がないことを証明 | 公共事業入札・許可申請 |
| その3(所得金額証明) | 所得金額を証明 | ローン申請、補助金など |
| その4(未納税額明細) | 未納がある場合の詳細 | 税務相談など |
地方税(住民税や固定資産税)に関しては、市区町村が「納税証明書」を発行します。
📋課税証明書と納税証明書のちがいまとめ
| 比較項目 | 課税証明書 | 納税証明書 |
|---|---|---|
| 発行機関 | 市区町村 | 税務署(国税)または市区町村(地方税) |
| 証明内容 | 所得・課税額 | 納付済み税額または未納の有無 |
| 対象税目 | 住民税 | 所得税・法人税・消費税など |
| いつ必要? | 所得状況を確認したいとき | 納税実績を証明したいとき |
| 発行対象者 | 住民登録がある人 | 納税した人 |
| 非課税者の扱い | 非課税証明書が発行可 | 発行されない(納税実績がないため) |
🏦どんな場面で使うの?

| 手続き・場面 | 必要になる証明書 |
|---|---|
| 住宅ローン・自動車ローン審査 | 課税証明書 or 納税証明書(金融機関による) |
| 保育園・幼稚園の入園申請 | 課税(所得)証明書 |
| 公共工事の入札・許可申請 | 納税証明書(未納がないことの証明) |
| 奨学金・学費減免申請 | 課税(所得)証明書 |
| 税務署への提出 | 納税証明書(その1〜その4) |
🏢発行方法のちがい
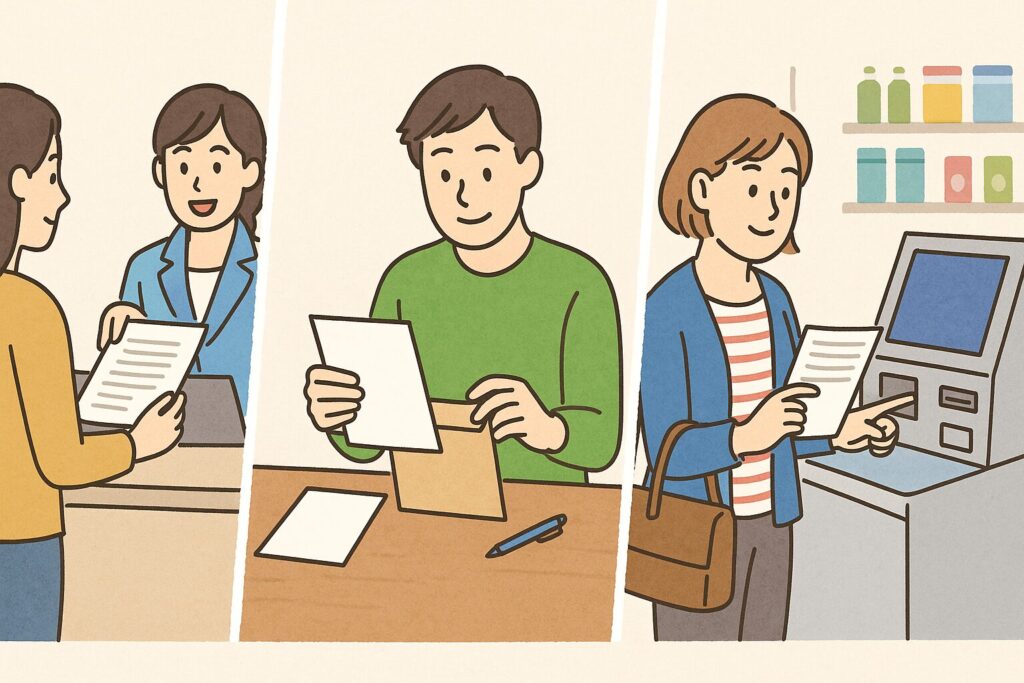
① 市区町村窓口で取得
- 本人確認書類を持参(マイナンバーカード・免許証など)
- 即日発行される(混雑時は待ち時間あり)
- 手数料は1通300〜400円前後
② コンビニ交付
- マイナンバーカード+暗証番号が必要
- 全国の主要コンビニで発行可能
- 対応時間:6:30〜23:00(自治体により異なる)
- 手数料は通常より安い(例:200円)
③ オンライン申請(マイナポータル等)
- 24時間申請可能
- 受取方法:郵送または窓口
- マイナンバーカード・電子証明書が必要
④ 郵送申請
- 申請書・本人確認書類のコピー・手数料(定額小為替)を送付
- 発行まで数日〜1週間程度かかる
📌申請時の注意点
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 代理人が申請する場合 | 委任状+代理人の本人確認書類が必要 |
| 必要書類 | 申請書、本人確認書類、手数料、(代理人の場合)委任状 |
| 年度の扱い | 令和7年度の証明書は「令和6年中の所得」を記載 |
| 発行期間 | 毎年6月頃から翌年5月末頃までが一般的 |
🗓年度別の注意点

課税証明書や納税証明書は年度ごとに発行されます。
「令和7年度」と書かれている場合、その内容は「令和6年(前年)」の所得や納税実績を示します。
| 年度 | 対象となる所得期間 | 証明書が使われる主な年 |
|---|---|---|
| 令和7年度 | 令和6年1月〜12月の所得 | 令和7年(2025年) |
| 令和6年度 | 令和5年1月〜12月の所得 | 令和6年(2024年) |
🏙特別区(例:港区・千代田区)の例
港区の場合(課税証明書)
- 港区役所 税務課窓口または港区マイナポータルで申請可能
- コンビニ交付対応(マイナンバーカード必須)
- 手数料:1通300円
千代田区の場合(納税証明書)
- 区民税課または収納課で発行
- 代理人申請には委任状が必要
- 手数料:1通300円
- 郵送・電子申請も可能
💡よくある質問(Q&A)
Q1. 「非課税証明書」とは違うの?
A. 非課税証明書は「税金がかかっていない(非課税)」ことを証明する書類です。
所得が一定以下の人に発行されるもので、課税証明書の一種です。
Q2. 会社員でも課税証明書は必要?
A. 勤務先が年末調整をしていても、個人でローン申請や補助金申請をする際に必要になることがあります。
Q3. どこで中身を確認できる?
A. 市区町村の窓口やオンラインで確認できます。
マイナンバーカードがあれば、コンビニ交付で手軽に発行可能です。
Q4. 国税の納税証明書はどこでもらうの?
A. 最寄りの税務署で発行できます。
または、国税庁の「e-Tax」からオンラインで申請・郵送受取も可能です。
Q5. 手数料はいくら?
| 証明書の種類 | 手数料の目安 |
|---|---|
| 課税(所得)証明書 | 300〜400円 |
| 納税証明書(国税) | 400円(税務署) |
| 納税証明書(地方税) | 300円前後 |
✉問い合わせ方法
☎電話で確認
- 各自治体や税務署に電話して確認可能
- 忙しい時期はつながりにくいため、午前中早めがおすすめ
🏢窓口相談
- 直接担当者と相談できるため、初めての方に安心
- 書き方が分からない場合も丁寧に案内してくれます
💻オンライン(e-Tax・マイナポータル)
- 24時間受付可能
- 発行済み証明書をデータで確認できる自治体もあります
🌸まとめ:混同しやすいけどポイントは3つ!
- 発行元が違う
→ 課税証明書=市区町村、納税証明書=税務署(国税)または自治体(地方税) - 証明している内容が違う
→ 課税=所得や課税額
→ 納税=実際に納めた金額 - 用途に応じて選ぶ
→ 所得証明が必要なら「課税証明書」
→ 納税実績を示すなら「納税証明書」
💬 ひとこと
「どっちの証明書かわからない…」そんなときは、
まず「どこに提出する書類なのか」を確認しましょう。
金融機関・役所・学校など、提出先ごとに求められる書類が違います。
無駄足を防ぐためにも、申請前に“どちらが必要か”をチェックしてから手続きするのがコツです✨
📌 あわせて読みたい